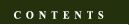
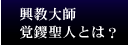
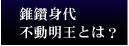
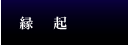
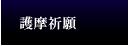
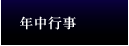
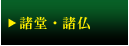
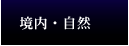
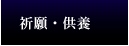
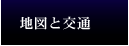
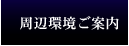
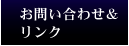
興教大師覚鑁聖人誕生の地、誕生院。
安産・会社開業・新車交通安全・・・。
新しいはじまりには、興教大師覚鑁聖人誕生の地「誕生院」で、新たな門出を祝い、健やかな未来を祈願致しませんか。
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
本堂 |
 |
 |
 |
 |
 |
足利三代将軍義満公の発願により、応永十二年(1405年)に創建されたが大友宗麟の戦火により壊滅。以来、大正十二年に建立されました。
|
 |
| 本堂 仏像のご紹介 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
錐鑽身代不動明王
(本尊)
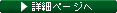 |
興教大師の身代りになって木像でありながら人間の生血を流されたお方で今なお霊験あらたかにして末世の私たちのために身代りとなり、大難は小難、小難は滅消へと御利益を導いて下さる大慈悲あふるるお不動さまであります。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
興教大師覚鑁聖人
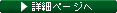 |
弘法大師の教理を継がれ、高野山を復興し、新義真言宗を開かれ、学問のほとけとして全国に祭られ仰がれておられるお方です。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
弘法大師空海上人
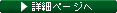 |
真言宗の開祖として全国に祀られ、宗教や宗派に関係なく様々な方が信仰されておられるお方です。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
布袋尊
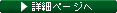 |
布袋尊は、悩みを戴きますと右手を参拝者に差出しておられ、あらゆる悩みごとを即滅して下さいます。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
三十六童子
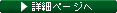 |
お不動さまの使者として仕える方々で、特に病気の時にはこの方々のお名前を呼ぶ事により御利益があると信仰されています。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
水子地蔵菩薩
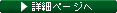 |
いつの日からか、目から涙を流されるようになり、多くの方々より、慈悲深きお地蔵さまとして信仰されています。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
子育て地蔵菩薩
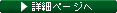 |
病気や怪我をしないように子ども達の成長を見守って下さるお地蔵様です。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
マリア観音菩薩
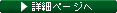 |
胸に十字架を刻み隠れキリシタンが信仰されたと伝えられる観音様です。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
金堂 |
 |
 |
 |
 |
 |
昭和四年より五ヶ年の歳月を要し、観心寺本堂の手法を範として造られた総欅造りのお堂です。御本尊は、当誕生院の地でお生まれになった宗祖興教大師覚鑁聖人をお祀りしております。
|
 |
| 金堂 仏像のご紹介 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
興教大師覚鑁聖人
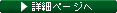 |
弘法大師の教理を継がれ、高野山を復興し、新義真言宗を開かれ、学問のほとけとして全国に祭られ仰がれておられるお方です。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
誕生院会館 |
 |
 |
 |
 |
 |
心なごむ空間、やすらぎの空間、コミニュケーションの場として利用できます。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 鐘樓堂 |
 |
 |
 |
総欅造りで3.52m四方の雄美な鐘樓堂と自然の円石を亀甲形に積み上げた高さ2.5mの石垣の奇観をお楽しみ頂けます。 |
|
 |
 |
| 鬼塚古墳 |
 |
 |
 |
古墳時代後期(六世紀後半ごろ)に構築されたもので、鹿島市内では最大、県内でも屈指の巨石墳であり、佐賀県の文化財に指定されております。 |
|
 |
 |
|
|
 |
| 産湯井戸 |
 |
 |
 |
| 興教大師御誕生の際、産湯に使用されたと伝えられる井戸。興教大師の誕生にあやかり、安産祈願の参拝も多くいらっしゃいます。 |
|
 |
 |
 |
| 十三仏像 |
 |
 |
 |
| 数多い仏さまの中から特に慈悲深く、私たちに直接救いの手を下さる仏さま方です。 |
|
 |
 |
| 修行大師 |
 |
 |
 |
覚鑁聖人が右手には金剛杖、左手には念珠を持って修行される姿の像です。(修行大師像) |
|

|